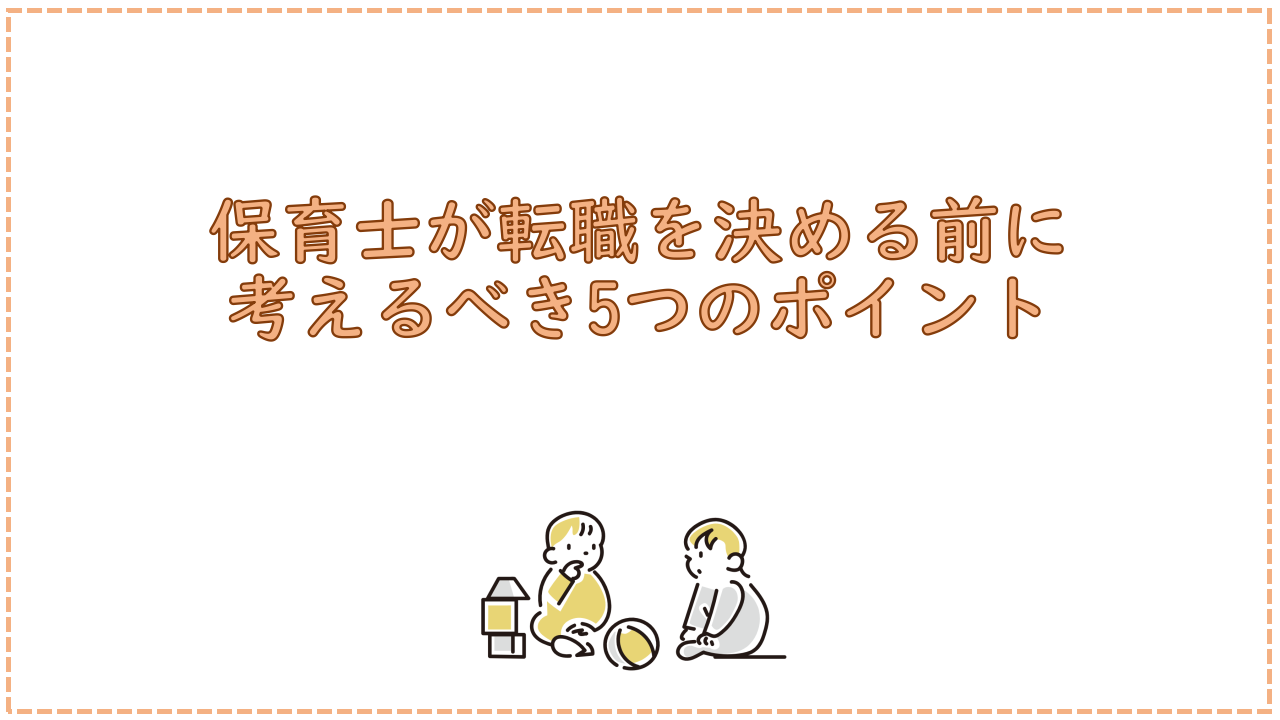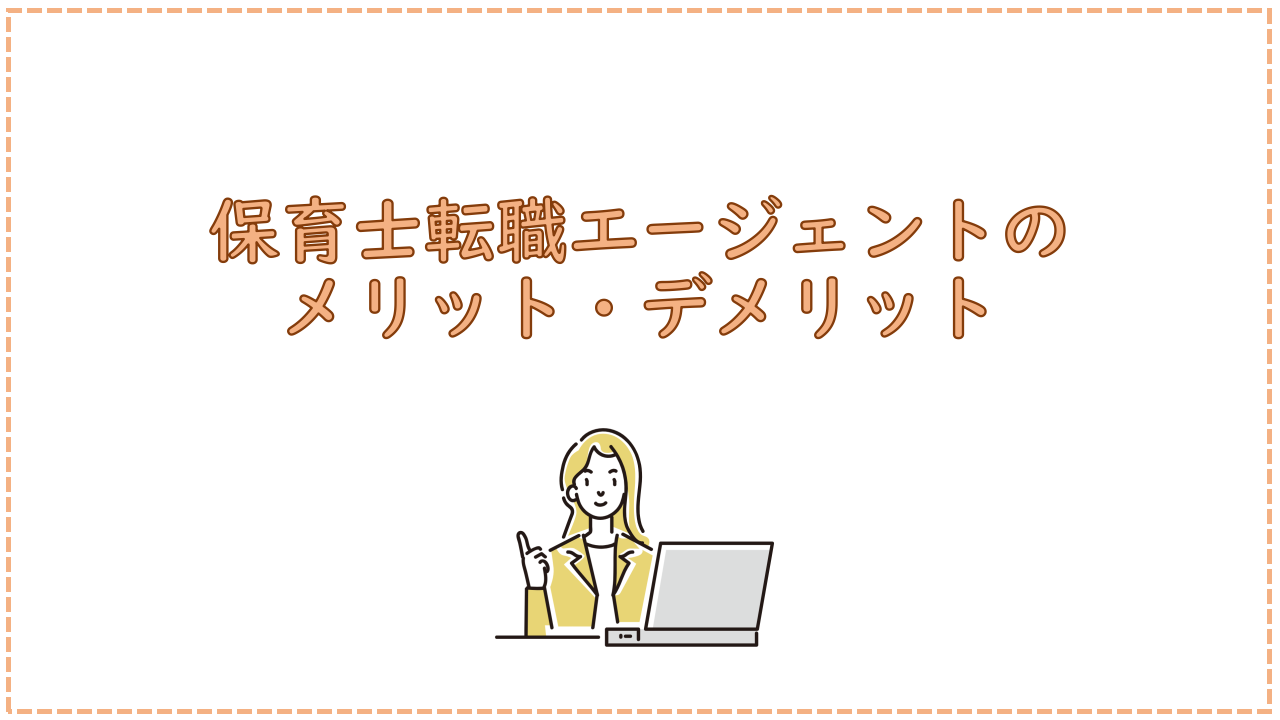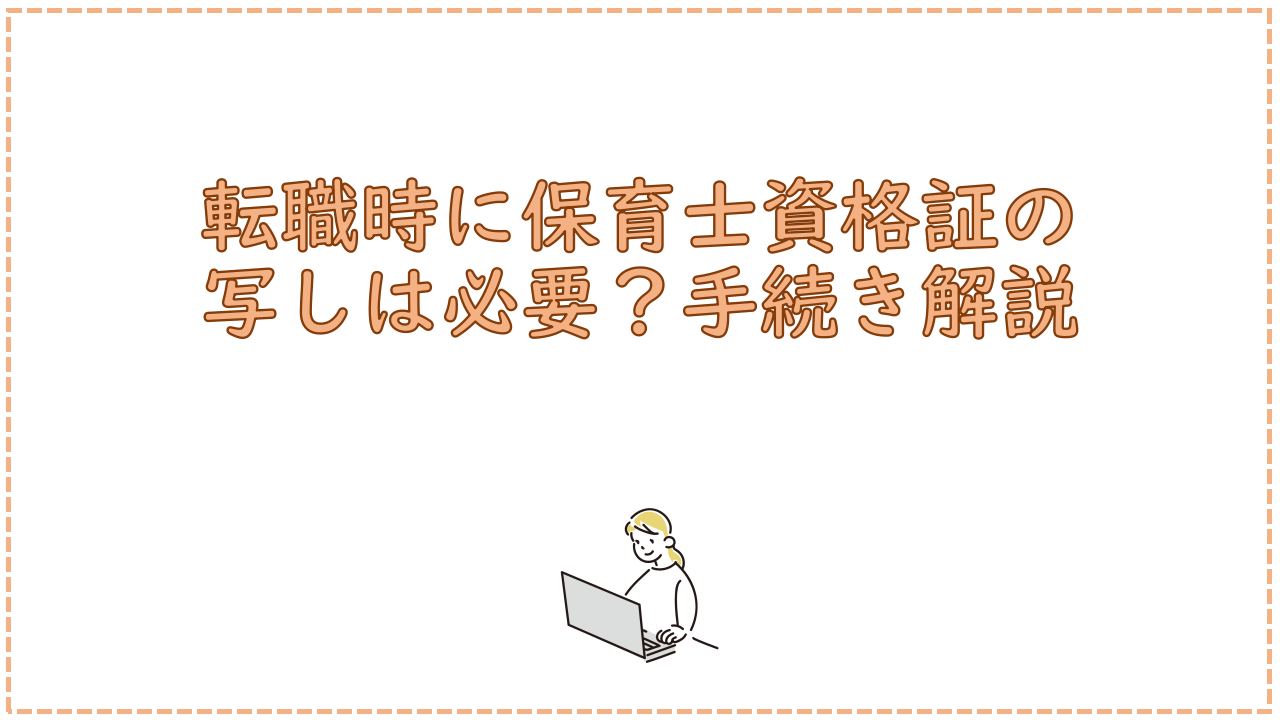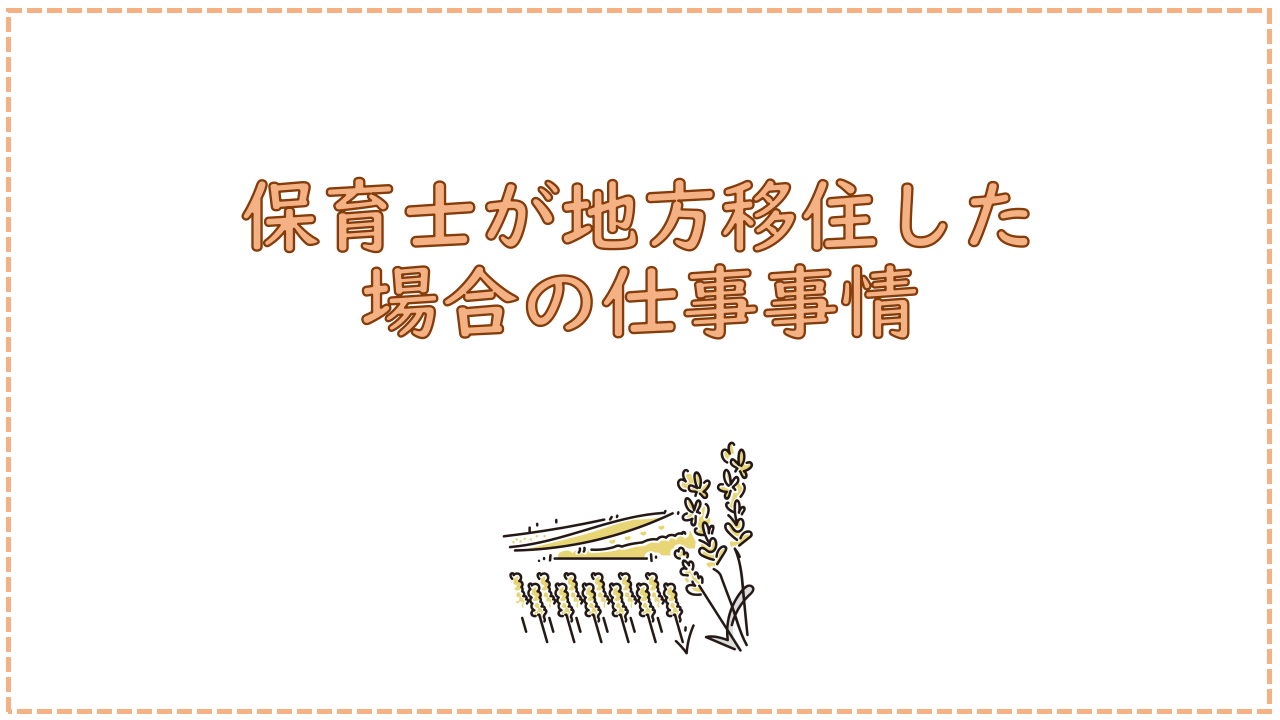病児・病後児保育専門施設で働く保育士の一日
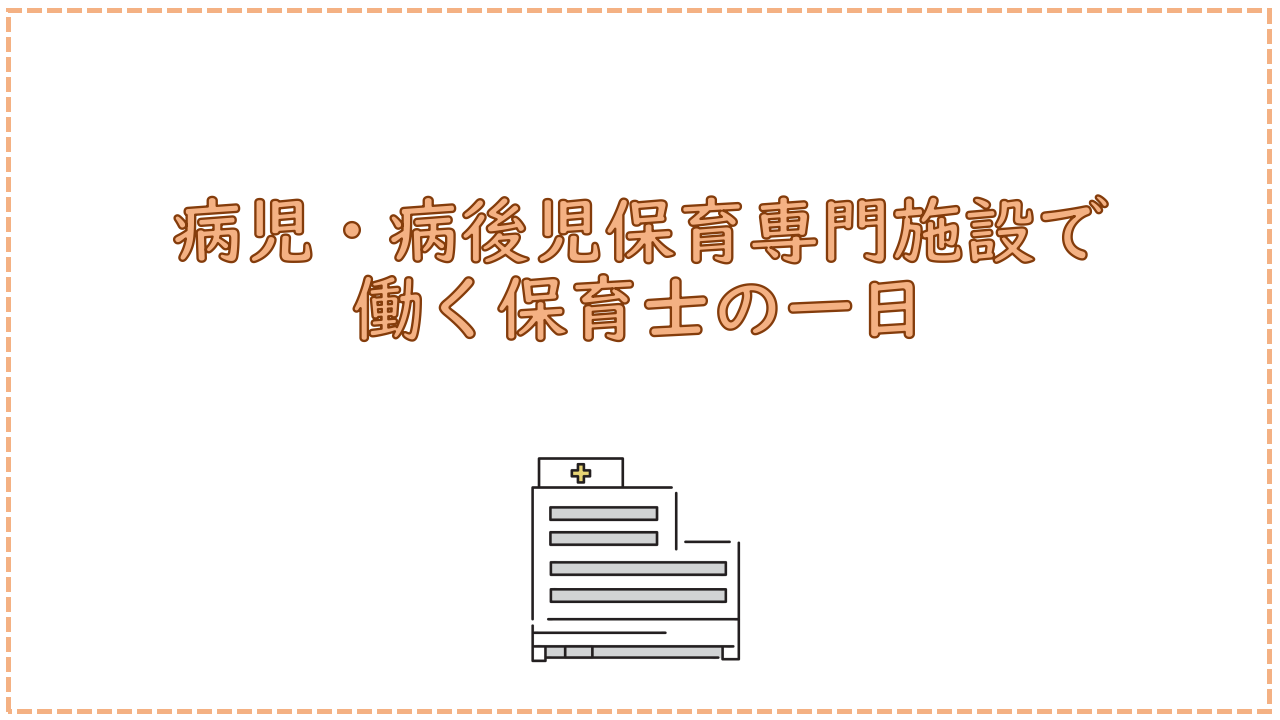
病児・病後児保育専門施設は、子どもが病気や病気の回復期にあるとき、一時的に保護者に代わって保育を行う場所です。一般の保育園とは異なり、体調が万全でない子どもを対象としているため、医療的な配慮や衛生管理が特に重要になります。ここでは、病児・病後児保育施設で働く保育士の一日の流れを、業務内容を中心に紹介します。
朝:受け入れ準備と健康状態の確認
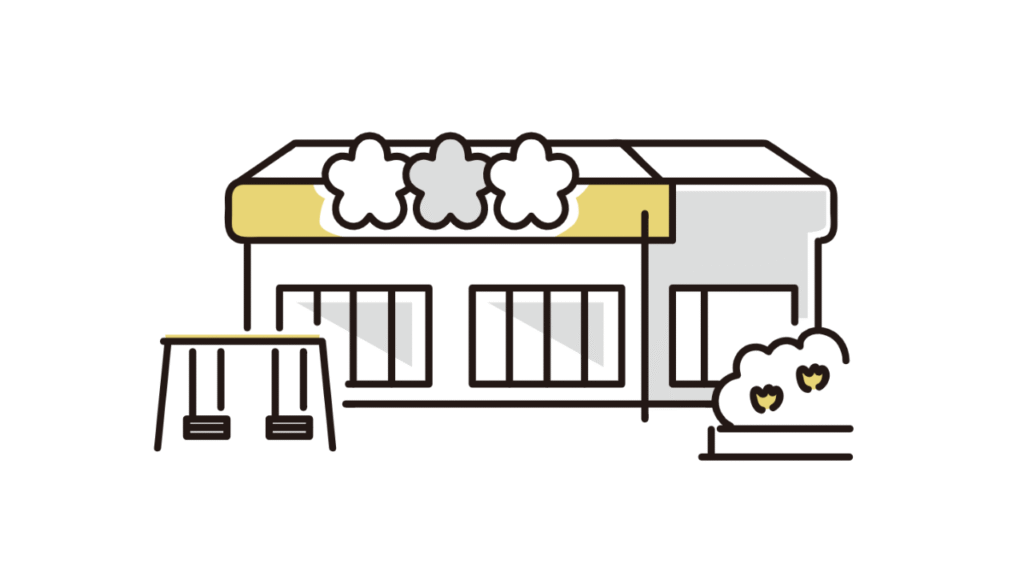
出勤後、保育士はまず当日の受け入れ予定を確認します。病児・病後児保育では、予約制を採用している施設が多く、その日の利用児数や病状によって業務内容が変化します。看護師や施設管理者と情報を共有し、体調に応じた受け入れ準備を進めます。
保育室の温度・湿度の確認や換気、加湿器の稼働確認など、環境面の調整も重要です。おもちゃや布団、机などの備品は、前日に消毒を終えていても、再度アルコールや次亜塩素酸水で拭き取りを行います。感染予防の徹底は、この施設で働く保育士にとって最も基本的な業務の一つです。
子どもが登園すると、保護者から症状の経過や服薬内容の確認を行い、看護師とともに健康チェックを実施します。体温測定や咳、顔色、機嫌などを細かく観察し、体調記録に残します。病状の変化を早期に把握するため、観察眼と記録力が求められます。
午前:安静を基本とした保育活動
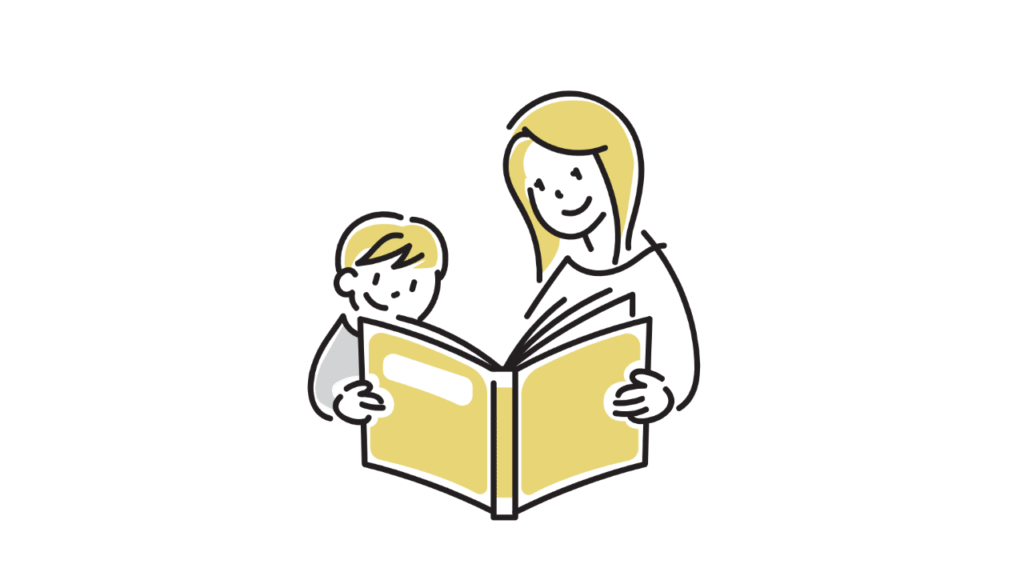
午前中の保育は、子どもの体調を最優先に進められます。元気な日常保育とは異なり、刺激を避け、静かに過ごせる活動を中心に行います。絵本の読み聞かせ、簡単なパズルや塗り絵など、体力を消耗しない遊びを選ぶのが一般的です。
また、子どもの体調や情緒が安定するよう、声のトーンや言葉選びにも配慮が求められます。体調が悪いときは、ちょっとした刺激や不安でも泣いてしまうことがあります。そうした場合、無理に遊びを続けるのではなく、ベッドや静養スペースで休ませる判断を行います。
看護師と連携しながら、体温や呼吸の状態を定期的に確認し、必要に応じて医療的なケアを補助する場面もあります。保育士は直接医療行為を行いませんが、観察や報告の精度が医療判断の支えになります。
昼:食事・服薬・午睡のサポート
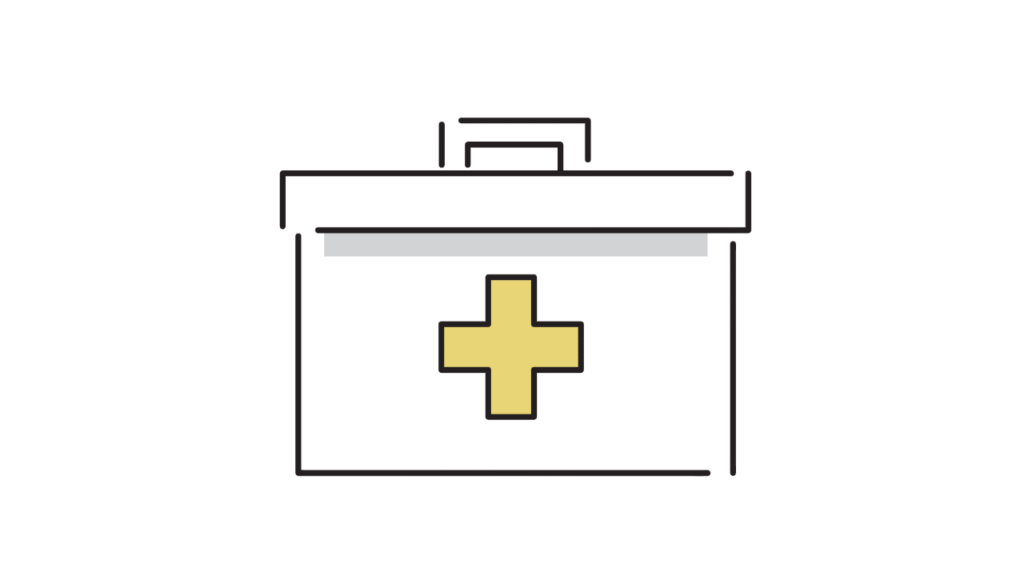
昼食は、子どもの体調に応じた内容で提供されます。食欲がない子どもには無理をさせず、食べられる範囲でサポートします。施設によっては、看護師や栄養士が管理する「やわらかめの食事」や「おかゆ」を用意しており、保育士はその配膳・見守りを行います。
食事後には服薬の時間があります。保育士は、保護者から預かった薬を看護師に引き継ぎ、服薬状況を記録します。間違いが起きないよう、二重チェック体制をとるのが一般的です。
昼食のあとは午睡(お昼寝)の時間です。子どもの体力回復にとって休息は欠かせないため、静かな環境づくりに注意します。照明を落とし、体温を確認しながら、安心して休めるよう見守ります。寝返りや呼吸の状態などを確認し、異変がないかを継続的にチェックします。
午後:体調変化の確認と帰宅準備
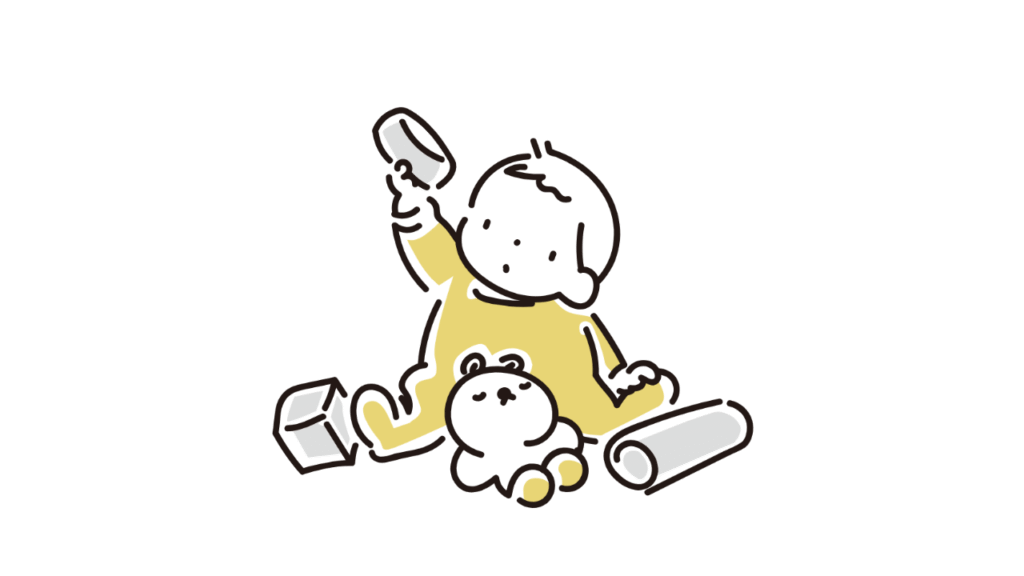
午後は、午睡後の体調観察から始まります。睡眠によって体調が回復する場合もあれば、発熱や倦怠感が再び現れる場合もあります。体温や機嫌の変化を記録し、必要に応じて看護師が医師と連絡を取ることもあります。
体調が安定していれば、静かな遊びや絵本の読み聞かせなどを再開します。元気になった子どもは笑顔を見せることもあり、その変化を観察して日誌に反映させます。病児・病後児保育では、保育士の観察記録が翌日の保育方針や医療判断に影響するため、記録はできるだけ客観的に行います。
お迎えの時間になると、保護者へ一日の様子を報告します。どのような遊びをしたか、食事量、午睡の時間、体温の推移などを詳細に伝えることで、家庭でのケアにつなげてもらいます。特に体調変化があった場合は、看護師からもあわせて説明を行うケースが多いです。
夕方:記録・消毒・翌日の準備
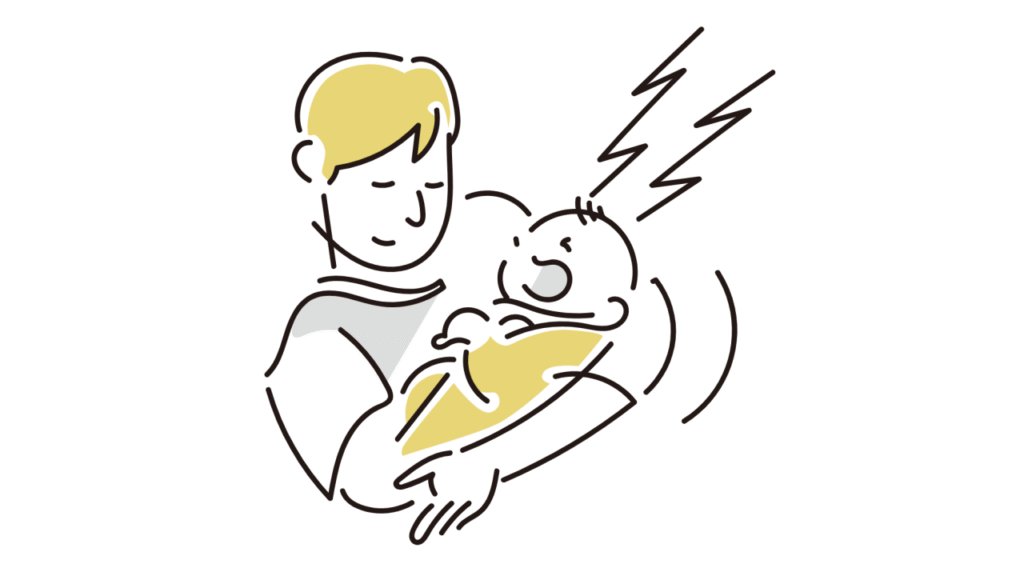
子どもたちを送り出した後、保育士は記録業務に移ります。体調や行動の記録、食事・服薬の内容、保護者への伝達事項などを整理し、看護師や管理者と共有します。医療的な配慮が必要な施設では、こうした記録が安全管理に直結します。
その後、保育室や使用した備品の清掃・消毒を行います。特に、感染症にかかっていた子どもが利用した場合は、念入りな消毒作業が求められます。布団カバーの洗濯、玩具の消毒、ドアノブや机のアルコール拭きなど、細部まで衛生管理を徹底します。
最後に翌日の受け入れ予定を確認し、看護師と打ち合わせをして業務を終えます。病児・病後児保育では、一日の終わりまで緊張感を持って対応することが多く、一般的な保育に比べて医療・衛生面での意識が高く求められる仕事です。
病児・病後児保育の保育士に求められる姿勢
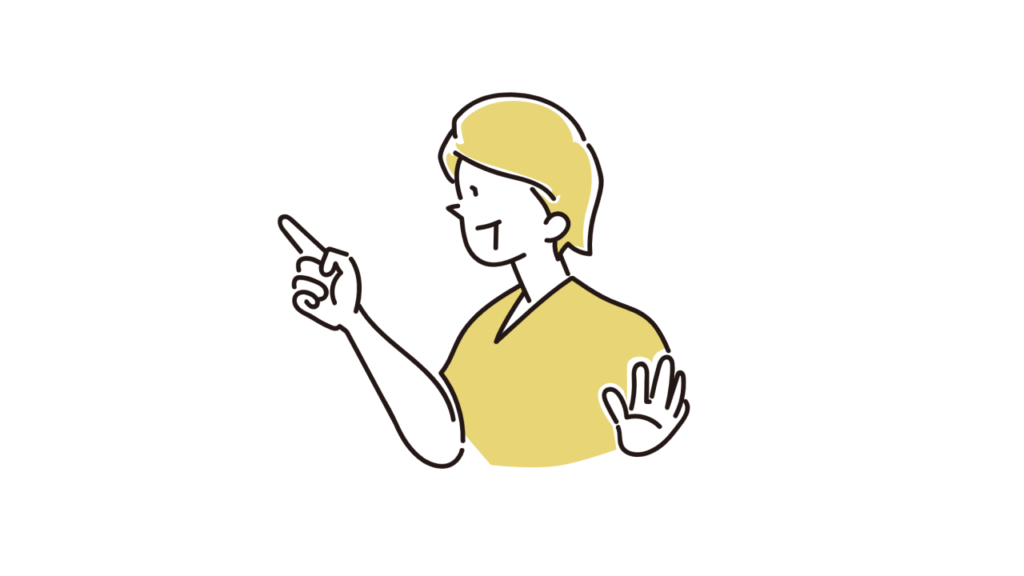
病児・病後児保育では、「安全」「清潔」「観察」の3点が基本軸となります。保育士は、子どもの体調変化を見逃さない観察力と、衛生面での徹底した管理意識が必要です。また、保護者との信頼関係を築くコミュニケーション力も欠かせません。
一方で、一般の保育園のように集団で活動することが少なく、静かに一人ひとりと向き合う時間が多いのも特徴です。そのため、「丁寧な対応」「落ち着いた判断力」「医療スタッフとの協調性」が求められます。
病児・病後児保育専門施設での一日は、穏やかな時間の中にも緊張感が伴います。子どもの安全を守りながら、回復を支援するという責任の大きな仕事ですが、その分やりがいも深い仕事といえるでしょう。